福岡ソフトバンクの浜口遥大投手が2025年11月11日に現役引退を表明した。
その背景にあるのが、国指定の難病「黄色靱帯骨化症」。今季4月に胸椎黄色靱帯骨化症の手術を受け、復帰を模索しながらも一軍マウンドに戻ることはできなかった。
ここ数年、プロ野球界では同じ病気を公表する投手が相次いでおり、「なぜ投手に多いのか?」という疑問も広がっている。
本記事では、黄色靱帯骨化症がどんな病気なのか、なぜ投手に多いと言われるのか、
そして過去にこの病気と闘った(または闘っている)選手たちについて整理する。
黄色靱帯骨化症とはどんな病気か
● 病気の正体
背骨(脊椎)の内側には、椎骨と椎骨の間をつなぐ「黄色靱帯」という靱帯がある。
黄色靱帯骨化症は、この黄色靱帯が徐々に骨のように硬く厚くなり(骨化)、脊柱管の中を通る脊髄や神経を圧迫してしまう病気だ。
主なポイントは以下の通り。
- 特に胸椎(背中側の背骨)で起こりやすい。
- 初期は足のしびれ、ふらつき、疲れやすさなど「あれ?疲れてるだけ?」と見過ごされやすい症状が多い。
- 進行すると、歩行障害、下半身の脱力、階段が上がれない、転びやすい、排尿障害など重い神経症状が出る。
- 骨化が画像で見つかっても、神経症状が出ていなければ「黄色靱帯骨化症」とは診断されない(=潜在的な骨化はもっと多いと考えられている)。
- 日本を含む東アジア人に多く、指定難病(指定難病68)として医療費助成の対象になっている。
● 原因は?
はっきりした原因はまだ解明されていないが、研究や臨床現場で指摘されている要因には次のようなものがある。
- 加齢変化(40代以降に多い)
- 遺伝的素因(家族内発症例の報告)
- 肥満・糖尿病などの代謝異常
- 長年にわたる姿勢・動作による反復ストレス
つまり「激しい運動をしたから必ずなる病気」ではないが、
脊椎に継続的な負荷がかかる人は、発症リスクに関係している可能性があると考えられている。
治療は、進行が軽度なら経過観察や保存的治療、
症状が進んで日常生活に支障が出る場合には、骨化した部分を削って脊髄の圧迫を取る外科手術が検討される。
(※具体的な治療方針は症状や部位により全く異なるため、必ず専門の整形外科・脊椎外科医の診察が必要)
なぜ「投手に多い」と言われるのか
実際、ここ数年に限っても、黄色靱帯骨化症を公表したプロ野球選手はほぼ全員が投手だ。
医療機関の解説や症例報告でも「プロ野球投手に多い傾向」が指摘されているが、これはまだ統計的に完全に証明された“事実”ではなく、現場からの経験的な傾向と考えるべきだ。
● 投手に多いと考えられる主な理由(仮説)
- 反復する全身のひねりと反り
投球動作は、胸椎〜腰椎を大きくひねり、反らし、急激にねじり戻す動きの連続。
背骨後方にある黄色靱帯には長年にわたって繰り返しストレスがかかり、
微細な損傷と修復を繰り返す中で骨化が進みやすい可能性があると考えられている。 - 筋力トレーニングと体格の変化
プロ投手は下半身・体幹を徹底的に鍛え、大柄な体格の選手も多い。
体重増加や筋量増加により脊椎への荷重が増え、靱帯への負担が蓄積しやすい。 - 前かがみ&反り返り姿勢の繰り返し
ブルペンや試合での投球数、遠征・移動、ベンチでの座位姿勢など、脊椎に負担のかかる時間が非常に長い。 - “見つかりやすい人たち”であること
定期的に精密検査を受けるエリートアスリートは、一般人よりも早期に発見されやすい。
「投手に多い」印象には、検査機会の多さも影響していると考えられる。
要するに、激しい投球動作+大きな体格+長年の負荷+検査機会の多さが重なり、
「投手で症例報告が目立つ」という状況になっているとみるのが妥当だろう。
浜口遥大と、黄色靱帯骨化症を公表した主なプロ野球選手
● 浜口遥大(ソフトバンク/DeNA)
- 2024年オフにDeNAからソフトバンクへトレード。
- 2025年4月、左肘手術とあわせて胸椎黄色靱帯骨化症の切除術を受ける。
- 二軍での登板は果たすも一軍登板なく、同年10月に戦力外、11月11日に現役引退を表明。
- 「難病を抱えながらの挑戦」となり、病気との戦いも引退理由の一つになった。
● その他、黄色靱帯骨化症を公表した主な投手たち
※いずれも公表情報に基づく一例であり、全員が同じ病態・予後ではない。
- 三嶋一輝(DeNA):2022年に胸椎黄色靱帯骨化症の手術。術後順調に復帰し、独自術式「MISHIMA手術」が話題に。
- 福敬登(中日):2022年に黄色靱帯骨化症の手術を公表、その後復帰登板。
- 谷岡竜平(巨人):2023年に手術を受け、同年限りで現役引退。
- 岩下大輝(ロッテ):2023年手術後、2024年に一軍マウンドへ復帰。
- 湯浅京己(阪神):2024年に胸椎黄色靱帯骨化症の手術を受けたことを公表。2025年復帰登板。
他にも、プロ・アマを問わず野球選手やスポーツ選手での報告例があり、
医学論文でも「野球投手における黄色靱帯骨化症の症例報告」が複数発表されている。
ファンとして知っておきたいポイント
- 命に関わる病気ではないが、「放置すると歩行困難や麻痺に至る可能性がある深刻な病気」である。
- 「投げ過ぎ=必ず発症」ではなく、体質・年齢・生活習慣など複数要因が絡むと考えられている。
- 早期には「足がもつれる」「長く歩くとつらい」「腰やお尻~足に原因不明のしびれ」など、腰痛や疲れと勘違いしやすい症状が多い。
- プロ選手の場合、違和感を我慢して投げ続けることで発見が遅れがちになるリスクがある。
もしファンやアマチュア選手が似た症状を感じても、記事を読んで自己診断するのではなく、整形外科・脊椎外科での専門的な検査・相談が必須であることは強調しておきたい。
おわりに──病気と向き合った投手たちへのリスペクトを
黄色靱帯骨化症は、まだ原因が完全には分かっていない難病であり、選手生命だけでなく、その後の人生の生活の質にも直結する重いテーマだ。
浜口遥大のように、手術やリハビリを経ても「もう一度プロのマウンドへ」という願いが叶わないケースもあれば、三嶋一輝や湯浅京己のように復帰して再び一軍で投げる例もある。
「なぜ投手に多いのか?」という問いの裏には、
過酷なトレーニングと投球を積み重ねてきた彼らのキャリアがある。
病名だけが一人歩きするのではなく、難病と向き合いながら挑戦を続けた投手たちへの敬意を込めて、状況を正しく理解していきたい。

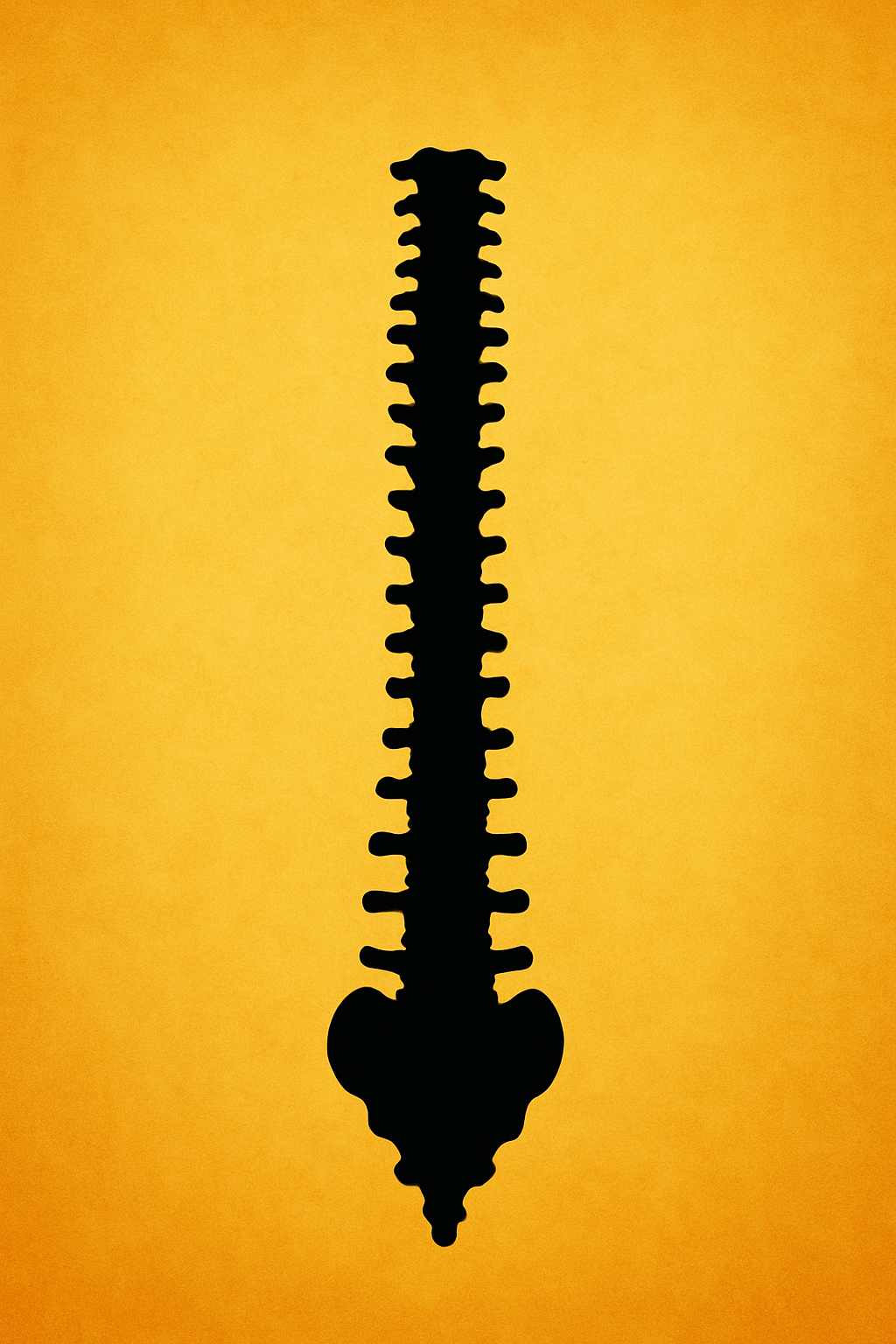


コメント