プロ野球の審判は、試合の主役ではない——はずなんだけど、ときどき主役の座を強奪していくのがこのお方、栄村孝康さん。1991年にプロ入り、通算1871試合に出場(2015年に現役引退)、現在はNPBのスーパーバイザーとして審判の技術指導に回っている大ベテランです。
伝説1:可変ストライクゾーン、通称“栄村ゾーン”
ネット界隈では、彼のストライクゾーンがよく動くという話題がしばしばネタ化され、ついには“栄村ゾーン”なんて愛称まで誕生。もちろん公式ルールにそんなゾーンはありませんが、「今日のゾーンは季節風並みに動く」なんてやゆが飛び交うのもまた、プロ野球の風物詩。
※ここでの“可変”はあくまでファン目線のネタ。実際にはどの審判にも“傾向”や“クセ”はあり、選手・観客・中継カメラの角度によって見え方が変わるもの……という前提はお忘れなく。
伝説2:名言(迷言?)「真実と事実という言葉もあるので」
語録も強い。2013年8月23日の中日—阪神(ナゴヤドーム)。右翼フェンス直撃っぽいマートンの打球が“ダイレクト捕球”判定され、和田監督が猛抗議→退場。試合後、その日の責任審判だった栄村さんの「真実と事実という言葉もあるので」というコメントが報じられ、ネットはざわつきました。判定自体は一塁塁審のものですが、言葉のパンチ力がすべてを持っていった事件です(この件が契機のひとつとなり、のちに外野フェンス際の打球もビデオ判定拡大へ)。動画のリンクを色々さがしたのですが、昔すぎてなかなか見つからなかったです。。。
重要試合で見せた“影響力”:3つの場面
① 2009年5月15日 楽天—日本ハム(Kスタ宮城)
山﨑武司が暴言で退場となった一件。試合後の「下手くそに下手くそって言って何が悪い」発言まで含めて、当時の野球ニュースをにぎわせました(のちに和解)。審判が“試合の空気”の一部だと痛感させられる出来事。
② 2009年7月14日 西武—楽天(西武ドーム)
無死満塁での本塁クロスプレー。一度ボールを落とした捕手について「完全捕球」と判定(球審:栄村さん)。9分間の猛抗議でも覆らず、西武はコミッショナーに質問状を提出。スコアは楽天8—6西武。記録だけ見ればただの1試合でも、ジャッジが物語の核になる代表例。
③ 2010年10月19日 パ・リーグCSファイナル第6戦
ロッテが3位から日本シリーズ進出を決めた夜。球審は栄村さん。極限の緊張下で両軍の“ゾーンの共有”を成立させるのがどれほど難しいか——そこへ飛び込んでいく胆力は、やっぱりプロフェッショナル。
“ゾーン”を笑いに変える観戦術
- 初回の数球は“今日の地図合わせ”:投手・捕手・主審が地図を同期していく時間。ここで首の傾げ合戦が始まったら、今日の実況はバラエティ寄り。
- ボール2からの“拡縮”に注目:追い込んでから外に1個広がるのか、高めに甘くなるのか。これが“栄村ゾーン”と呼ばれる印象の源泉。
- ベンチワークを見る:捕手がミット位置で学習しにいったり、打者が立ち位置を数センチ刻むのはゾーン対応のサイン。
それでも、最後は“審判がスポーツを進める”
皮肉やネタの対象になりやすいのも事実ですが、栄村さんはオールスター3度、日本シリーズも担当したトップカテゴリーの審判。引退後はスーパーバイザーとして、後進の育成にまわっています。「審判もまたプロ」——この当たり前を教えてくれる存在でもあります。往年のプロ野球ファンからすると栄村さんのストライクゾーンもエンタメの一つでした。引退してしまってさみしいです。最近はこれくらい個性の強い審判っていうと、白井さんか敷田さんくらいですもんね。。。
参考リンク
- プロフィール・現在職(NPB公式):NPB|栄村 孝康 / Wikipedia
- 2009/5/15 楽天—日本ハムの退場劇:スポニチ(Webアーカイブ)
- 2009/7/14 西武—楽天の本塁判定・試合結果:NPB公式スコア / 抗議・質問状の報道:SANSPO(Webアーカイブ)
- 2010/10/19 パCSファイナル第6戦(球審:栄村):Wikipedia(第6戦の審判表記あり) / NPB公式スコア
- “可変ゾーン”“栄村ゾーン”のネットスラング解説:新・なんJ用語集「可変ゾーン」 / 同「スリービレッジ」
- 2013/8/23 中日—阪神の判定騒動と制度改正の流れ:デイリースポーツ(ビデオ判定拡大の報) / 引用された発言の紹介:なんJまとめ記事
(注)本記事は野球ファン的な“ネタ視点”を織り交ぜた読み物です。個別の判定評価は最終的に公式記録・リーグ裁定に従います。


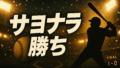

コメント